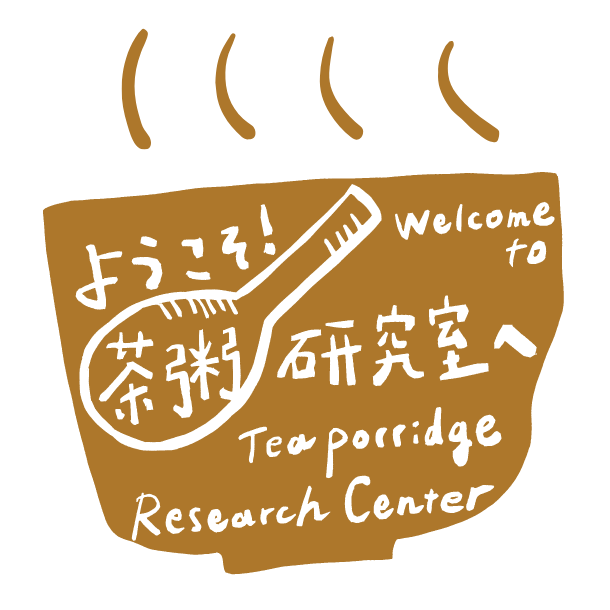醤油と鰹節の発祥地。梅、みかん、山椒の生産量も堂々の日本一。
そんなことちっとも自慢しない超絶謙虚な和歌山の人たち。
ところが茶粥の話になるとみんなアツく語りだす。
平地が少ないのに江戸時代の石高は全国5位。もしかして農民は茶粥を食べて年貢を納めていたのかも?そしてこの茶粥こそが人々を謙虚にしているのかも?
県民性を茶粥で紐解くべく、あらゆる茶粥を採集するこのコーナー。
記念すべき第1回は和歌山県みなべの梅農家、宮本とも子さんです。
梅農家の限りなく自給自足な茶粥
宮本さんの故郷は和歌山県最南端にある串本町。地元の世界的プロサーファーが「難所」と認め、中上健次が代表作のタイトルにも冠した枯木灘沿岸の中でも最も荒々しい和深という地区の、海にほど近い漁師の家で宮本さんは育った(つまり荒々しさの極みのような場所ってことです)。
宮本さんには妹がいる。小さな姉妹に茶粥をつくってくれたのは漁師のおじいちゃんだった。何十マイルも黒潮に乗ってカツオを追いかける漁が終わり、伊勢海老漁に切り変わる秋から春先にかけて、姉妹の朝ごはんは、たいてい茶粥だった。ちなみに、漁の繁忙期は朝はパン食。晩ごはんには茶粥を食べる、そんな暮らしだったという。
茶粥は沸かしたお茶でお粥を炊くというシンプルな食べ物。けれど、ベースになるお茶や、つけあわせが家庭と地域によって異なる。だから無限の組み合わせがあるとも言える。この辺りの話になると、いつもは何一つ自慢しない謙虚な人々も、やおら「つけあわせ」自慢をはじめる。
その瞬間が個人的にはとても好きだ。決して「お宅のより、うちのがおいしいよ」という競争心ではなく「うちのがおいしいから、食べさせたいよ〜」というシェアリング精神からくるものだから。ああなんて愛しく良き人なんだろうか、和歌山県人って!
「串本周辺では、ふる漬けを刻んでカツオ節や生姜醤油を混ぜたものがマスト。この辺りのスーパーでは、ふる漬けに生姜をのせたのも売ってます。あと、さんまやキビナゴの丸干し。それと茶がゆを一緒に食べるんです」。
 今日のつけあわせは2週間前に仕込んだばかりの自家製金山寺みそ、ふきの佃煮、古漬けの生姜醤油あえ、梅干し2種(白干し、しそ漬け)、太刀魚の干物と天ぷら(白身魚のすり身のを天ぷらと呼ぶ)、鰹節の醤油かけ。
今日のつけあわせは2週間前に仕込んだばかりの自家製金山寺みそ、ふきの佃煮、古漬けの生姜醤油あえ、梅干し2種(白干し、しそ漬け)、太刀魚の干物と天ぷら(白身魚のすり身のを天ぷらと呼ぶ)、鰹節の醤油かけ。


農家に嫁いだ今となっては自分でお茶を摘んで製茶するぐらいになったが、子どもの頃はやはりお茶は買っていたそうだ。
「串本の商店街にあるお茶屋さんでお茶を買って、紐のついたちゃんぶくろにお茶を入れて、お茶を沸かしていました。お茶は、ほうじ茶です。秋になってケツメイシの種が採れる頃には、たまにハブ茶でもおかいさんを炊いてました」。
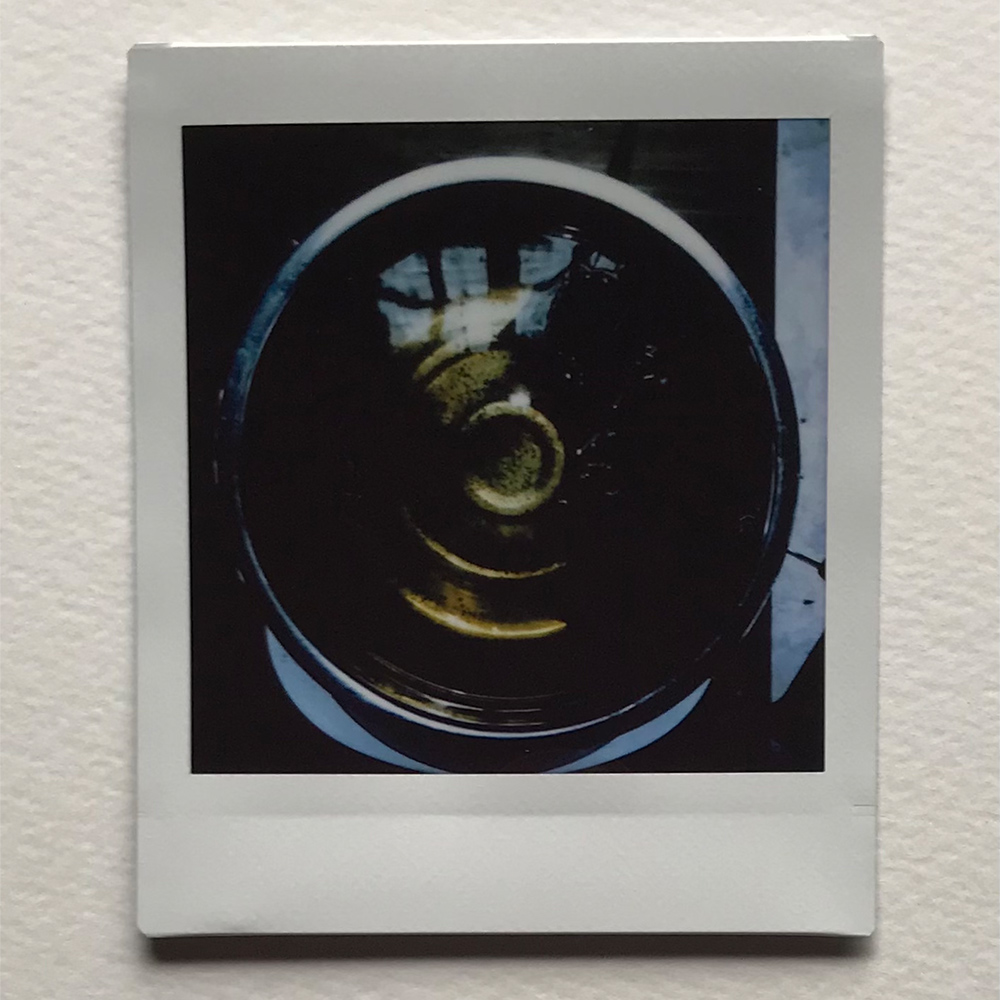
宮本さんは今ももちろん茶粥を食べているが、旦那さんが茶粥嫌いのため茶粥を食べる頻度は減った。どうやら茶粥は好きか嫌いかにきっぱりと別れる食べ物のようで、茶粥が大好きでアツく語り出す人と、嫌いだから絶対食べないという派にきっぱりと別れる。
嫌いの理由を紐解くと「しょっちゅう食べていたから」とか、「茶粥の中の煮崩れた芋がドロドロで嫌だった」とか、そんな話が出てくる。
「妹も茶粥が嫌いで、白いご飯の上に茶粥をちょこっとのせる食べ方をしてましたね。あとはたまに小麦粉を練ったものをおかいさんに入れて(「うけじゃ」と呼ぶ)くれていて、それをお皿にとり分けて、きなこと砂糖をまぶしてデザートがわりにしてたこともあります」
なんと斬新な食べ方なのか。和歌山の茶粥文化、海のように広くて深い。
「小さい頃はゴンドウクジラの干物を七輪で炙って、脂が落ちて火と煙がたって…という光景を近所でよく見ました。今住んでいるみなべではクジラを食べないし、夫も苦手みたいです」
串本とみなべ町は同じ南紀に位置するとはいえ、約60キロ離れている。随分違う食文化があるようだ。
ちなみに宮本さんのお子さんは、茶粥を食べたり、食べなかったりだそうだが、たまにお母さんが茶粥を食べる姿を、いつか思い出すに違いない。だってDNAは知っているのだから。

フェローのプロフィール
宮本とも子さん
和歌山県みなべ町で除草剤不使用・減農薬の完熟梅を栽培する宮本農園に勤務。梅の受粉には養蜂したニホンミツバチを使う昔ながらの環境に優しい農業を営んでいる。薄皮の完熟梅を熟成させた梅干しの加工や金山寺みそやキムチなどの発酵食品のワークショップ講師も務める。